■ FIXED BIKE BLUES-その1:ひとつのローラー台の死- ― 2017/03/12
今は廃刊となっている『月刊ニューサイクリング』誌の2013年5月号に掲載された作品です。また、表紙の写真は、妻が1995年夏、アイルランド・アラン島にて撮影したものです。
====================================================

ひとつのローラー台の死
2013年1月15日、かつてこの国では成人の日と定められていた日に、27年間使用した僕の3本ローラー台(MINOURA TRAINER)が破損した。数年前から使うたびに大きな回転音を出すようになっていた。それでも我慢していたが、とうとう円筒ローラーの接合部分が剥がれ、ホイールを回転させてもローラーが空転するようになってしまった。

僕が20歳になった1985年の大晦日に、生まれて初めて購入した3本ローラー台だった。当時、バイクショップ「富山サイクリングセンター」は大晦日も営業していたわけだ。そういえば元日も「初乗り」と称して、オッちゃん(上野茂氏:店長であり、ブランド「ROMAN」のフレームビルダー)と雪の中、サイクリングしていたっけ。それ以降、僕のローラー台は満27歳と15日働いてくれた。
最初はバランスを取りながらのペダリング練習からスタートした。しばらくすると両手を離して上着の着脱もできるようになり、ペダリングしながら新聞を読んだり、トーストを食べたりすることもできるようになった。一度だけバランスを崩し落車したことがあった。スーパーチャンピオン(*1)のチューブラーリム(*2)(後輪)が湾曲し、円筒ローラーに傷が付いた。それから27年、僕自身の打撲はその後回復し、成人の日も訳の分からないハッピーマンデーとやらに変更されたが、ローラー台の傷は今日も残っている。
話題がちょっと逸れるが、27歳という年齢は、音楽界にとって鬼門の年齢だ。ジミ・ヘンドリックスが急死したのも27歳。ザ・ローリング・ストーンズのブライアン・ジョーンズ、ジャニス・ジョップリン、ザ・ドアーズのジム・モリソン、ニルヴァーナのカート・コベイン、そして最近ではエイミー・ワインハウスの急死が記憶に新しい。そして古くはブルーズ界の伝説、ロバート・ジョンソンが1938年の8月16日、女性問題のもつれから毒殺されたのも27歳だった。彼はミシシッピ州クラークスデールという町の、とある「クロスロード」(十字路)にて、ブルーズの悪魔にギターテクニックと引き換えに魂を売ったといわれている。
27年間という時間の長さを、短いと考えるか長いと考えるかは、各々読者の判断に任せる。僕個人の意見を言わせてもらえれば、人間は無論のこと、道具としてのローラー台であろうとも、それは実存的価値を持つには充分な時間ということだ。もうこれ以上何もしてくれなくてもいい。唯そこに居てくれればそれでいい。
[用語解説]
*1 スーパーチャンピオン 自転車ホイールリムメーカー名。1980年代に幕を閉じた。
■ FIXED BIKE BLUES-その2:ピストバイクからフィクスドバイクへ- ― 2017/03/12
今は廃刊となっている『月刊ニューサイクリング』誌の2013年5月号に掲載された作品です。
====================================================
ピストバイクからフィクスドバイクへ
僕の住んでいる富山県は、冬季、雪に閉ざされる。
12月から2月までは屋外をバイクに乗って走ることが困難だ。この時期如何にしてフィットネスレベルを維持し、否、さらにパフォーマンスを高めるかが、雪国サイクリストとしての課題なのだ。
僕のメニューは、ランニング、ヒンズースクワット中心のウエイト・トレーニング、そして固定ギア(*1)のピストバイクによるローラー台トレーニングだ。ローラー台トレーニングは、120から130回転/分のペダリングで2分から5分もがくインターバルトレーニングを1時間行うものだ。これを飽きもせず27年間継続して行ってきた。ちなみにヒンズースクワットは大腿部が床と平行になるまで腰を落とすフルスクワットで1000回、時間では約1時間。これも27年間継続している。


冬場にこれだけルーチンなトレーニングをやっていれば、バイクで屋外を走ることができる春の到来が、「どれだけ歓喜に満ちたものなのか!」想像していただけるであろうか。
ランニングは多少路面に雪があったり、凍結していたりしても可能だ。雪国富山県とはいえ、遥か極北の冬と異なり、雪雲のさらに上空には一応太陽が昇っている。曇天でたとえ僅かな太陽光線であったとしても、それを浴びることができることは有り難い。また、雪によって空気中の塵などが払拭され、加えて適度な湿り気をもたらしてくれる。そして何よりも静かだ。雪が音を吸収してくれるのだ。そんな環境の中でランニングしていると、「何故、走るのか?」という疑問が湧いてこない。それより先に「走れること、それだけでうれしい。」という気持ちが湧いてくるからだ。
春がめぐり、バイクで走ることができるようになった時も然り。「走ることができる。これは何と有り難い事か!」という気持ちが湧いてくるのだ。人間は如何なる環境にも、身体のみならず精神をも適応させることができるのだとつくづく思う。世界には至るところにブルーズが流れているのだ。
多少なりとも自転車競技を続けてきた者として、冬場のオフシーズンは、固定ギアによるペダリングスキル練習やペダリング高回転練習は必須だ。ところが最近は、ピストバイクに対する世間の目が極めて厳しい。ピストバイクにとってブルーズィーな時代となった。
ブレーキを装着しないで公道を走り事故を起す輩が増えたためだ。言語道断である。ピストバイクが違法なのではない。ピストバイクの違法な乗り手が存在するのだ。しかし一方で、ピストバイクへの度を越した悪意の目にも少々危機感を感じる。
それは物事を一くくりで見がちの言わば全体主義の匂いだ。「ピストバイクというものは・・」「男というものは・・」「中国人というものは・・」「タバコというものは・・」「今どき、スマートフォンを持たない人なんて・・」等々。全てを単純・一般化して捉える思考と圧力の恐怖だ。
ピストバイクとは、トラック(自転車競技場)で競い合うためのバイクだ。トラック内ではブレーキを装備しない。トラック内でのブレーキングは危険だからである。公道を走る際は、必ず前後ブレーキ、ライト、反射鏡を付けなければならない。僕は毎日、トラックで練習できる環境にいるわけではないので、普段はブレーキを付けてのロードトレーニングをせざるを得ない。そして競技会の時はブレーキを外して参戦してきた。
アルミ板でサンドイッチして取り付けるタイプのブレーキ本体は、機能的にも視覚的にも個人的に好きではない。だから、ブリッジやフォーククラウン(*2)に最初からブレーキ本体の軸を通すことができるよう、ロードバイク用のブリッジ及びフォーククラウンでピストフレームを作ってもらった。よって僕のピストフレームはNJS(*3)規格ではない。


20歳代の時、固定ギアに馴染めず、サンシン(*4)製の両側にギアを取り付けることのできるハブを使って(今でも使用している)、片方には固定ギア、もう片方にはシングルフリーギア(*5)を取り付け、使い分けていた。
ところがシングルフリーギアというものは厄介なものである。歯数を変えたい時、固定ギアのように簡単に取替えができない。自分なりに一生懸命練習し、誠実に競技性を突き詰めていった結果、固定ギアにたどり着いた。一度雨の中の長時間練習で、シングルフリーギアのラチェット(*6)がうまく作動しなくなり、クランク(*7)が空転して走ることができなくなった経験もある。そもそもシングルフリーは実用車向けの部品であり、スポーツ向けではない。
現在は両側とも固定ギアで歯数を二種類にし、練習メニューやコースによって使い分けている。年齢を重ねるたびに最近はトラック競技会参戦もほとんど無くなってきた。しかし若かりし頃あんなに馴染めなかった固定ギアだったのに、今ではその簡明直截な感覚が心身ともに気持ちよく、依然としてピストバイクを走らせている。
最近の僕のピストバイクは、トラックを走るよりもロードを走ることの多いので、フィクスドバイク(FIXED BIKE、固定ギアのバイク)と呼んだほうが適当である。
[用語解説]
*1 固定ギア 競輪用自転車などトラック(ピスト)を走る自転車のギア。空転せず走っている時は脚の回転を止めることができない。空転するギアをフリーギアという。
*2 ブリッジ及びフォーククラウン フレームの部位。ブレーキ本体を取り付ける箇所
*3 NJS 日本自転車振興会の略称。競輪用自転車はNJS規格のフレーム及びパーツを使用しなければならない。NJS規格のフレームだとブレーキ本体を取り付けることが困難である。
*4 サンシン 自転車のハブ(ホイールの軸部分)のメーカー
*5 シングルフリーギア ギア板が一枚の非固定式ギア。通常実用車に使用されている。
*6 ラチェット フリーギアが空転したり回転したり機能するためには、ギア本体の中に爪が必要である。その爪をラチェットという。
*7 クランク ペダルがついている左右2本の棒
■ FIXED BIKE BLUES-その3:限られた条件の中で- ― 2017/03/12
今は廃刊となっている『月刊ニューサイクリング』誌の2013年5月号に掲載された作品です。
====================================================
限られた条件の中で
時が流れ、ロードバイクの世界では多段フリー(*1)化、STI変速(*2)、そして電動変速と物凄いスピードで機材が進化し、今も進行中である。部品のコンポーネント化によって、どこか一部を取り替えたいと思っても、全体を一緒に交換しなければパフォーマンスを維持することができない時代になった。

一つ一つの部品のコストも以前より高くなってきたようで(正確に言えば、ハイエンドの部品の価格が特に高くなってきていると思う)、一般ユーザーがロードバイクを維持していくだけでも大変になってきた。少なくとも僕はそうである。何か経済のカラクリに個人が翻弄されているような感さえ覚える。
そんな状況の中で、ふと僕のフィクスドバイクを眺めれば、それは日進月歩の機材進化の流れに全く取り残された、というよりも変化することを自ら拒み続けてきた、云わばFIXEDな頑固者の姿があった。この頑固者はめっぽうランニングコストが低い。且つメンテナンスが容易で工具も少なく済む。こういうのを「ネオ・シンプル」とでも呼べばよいのだろうか。
巷には便利なモノが溢れている。変速機もその一つ。且つ、その便利なものを所有できない立場でもない。欲しいと思えば手に入れることも可能だ。しかし敢えて、積極的に所有しないという姿勢を維持する。そのような意味で「ネオ・シンプル」。
20世紀までは、できるだけ多くのモノを所有することが豊かさのスタンダードだったようだ。しかし21世紀の今は違うと思う。これからはモノに束縛されない、モノに振り回されない自由度が豊かさの指標だ。自由(FREE)を感じる具象物が固定ギア(FIXED)というのもパラドックスで面白いと思うんだけど。

フィクスドバイクは、19世紀後半に登場したチェーン使用のセーフティ型自転車以来、駆動システムとしてはほとんど変化していない固定ギアのバイクだ。セーフティ型自転車の発明者であるイギリス人H.J.ローソンは、自身の開発したローソン3号車にBicycletteとフランス語で命名した。これが英単語Bicycleの語源である。
世界最大の自転車レースであるツール・ド・フランス黎明期においても、使用されていた自転車は通常、固定ギアで、当然変速機など使用されていない。ツール・ド・フランス創始者のアンリ・デグランジュは「選手は自転車を使ってレースをしているのであって、自転車に使われてはいけない」と言ったそうだ。彼に言わせれば、変速機を使用することは卑怯だということらしい。そして1936年大会まで変速機の使用を禁止していた。既に変速機が世に出回っていたにもかかわらず、敢えてそれを拒み続けたということだ。これこそ「ネオ・シンプル」だ。

ある歴史学者が言っていた。「自身の歴史を忘れた民族は滅ぶ。」
あるサイクリストが言っていた。「原点を忘れた文化は衰退する。」
あと10数年もすれば僕も頑固爺さんの年金生活に突入する。公的年金には不安を感じるので、自助努力として只今せっせと私的年金の掛け金も支払っている。体力の続く限りは働いて収入を得たいと思っているが(そのためにも、バイクで健康・体力を維持しているのだ)、高齢になっても若かりし頃と同じライフスタイルを望むことはできないし、またそうすべきではない。人生も自転車も限られた条件、限られたギアで生きねばならないのだし、またそうすべきなのだ。

不可避であるエイジングは受容しなくてはいけない。正真正銘、本物のブルーズは懐の深さを前提としているものだ。でも、それでも僕は年老いても、一生、死ぬまで競走用自転車に乗っていたい。日向ぼっこで暖まる老人じゃなく、自ら内燃・発熱する年老いた挑戦者でありたい。何故ならば、人間は哺乳類、自ら体温を保つ恒温動物だからだ。
そんな老年期における自転車ライフを考えると、僕はフィクスドバイクがピッタリなんじゃないかと思う。変速機付きロードバイクは、あまりにも時間の流れもお金の流れも速すぎると思うのだ。身の丈の限られた収入の中で、贅沢をせず、忍耐強く、世間に流されることも少なく(時には流れに身を任せ)、マイペース、マイウェイで、時に昔を懐かしみつつ、モノを大切にし、しかし自分自身との戦いに挑み続け、いろんな意味で無駄な贅肉をそぎ落とした、そして頑なに、自分自身に徹する老人。
喩えて言うならばヘミングウェイ作『老人と海』のサンチャゴ翁のような老人。そんな誇りを秘めた老人のコンペティション・バイクには、フィクスドバイクがフィットすると僕は思う。
*音楽の一ジャンルとしてのBluesは、わが国では一般的には「ブルース」と表記されているが、正しくはブルーズ(blu:z)である・本稿では筆者の思いを込めて、あえて「ブルーズ」と表記した。
▽参考資料
佐野裕二著:自転車の文化史、中公文庫、1988
安家達也著:ツール100話、未知谷、2003
[用語解説]
*1 多段フリー ギアが複数枚付いていて変速可能のフリーギア
*2 STI変速 シマノ・トータル・インテグレーションの略称。自転車パーツメーカーのシマノが開発した、ブレーキレバーで変速も可能のシステム。
■ FIXED BIKE BLUES-その4:写真説明- ― 2017/03/12
今は廃刊となっている『月刊ニューサイクリング』誌の2013年5月号に掲載された作品です。
====================================================
●写真説明
①フィクスドバイク全体のフォルム
(フレーム:ローマン、富山サイクリングセンター上野茂氏製作)


ドロップハンドルバーとブルホーン及びDHバー(*1)を兼用することができるように、フレーム形状をファニーバイク型(*2)にした。ドロップハンドルを装着した全体のフォルムは、1988年ソウルオリンピック、スプリントで優勝したL.ヘスリッヒや、1990年世界選手権前橋大会、スプリントで優勝したM.ヒューブナーなど、かつて東ドイツの大型選手が乗っていた前下がりのシルバーフレームを意識した。僕は足元にも及ばないけれど・・・
②サンシンのリアハブ


左右両方に固定ギアを装着している。ホイールの着脱が容易にできるように、シャフトを中空シャフトにして、クイックレリーズレバー(*3)にしてある。また、万が一に備え、チェーン引きも装備している。勿論、トラックを走る際は、ナット止めソリッドシャフトのハブを装備したチューブラーホイールに交換する
③ダイナモ内蔵フロントハブ

現在は雪に閉ざされた冬季のため、ローラー台トレーニングシーズン。ライト本体は取り外してある
④ヘッドおよびフォーク

加齢と共に、深い前傾姿勢が困難になってきた。昨年、以前使用していたフォークを再利用しコラムを入れアップライドポジションにした。感触も良くなってきたので当面はこのスケルトン(*4)で行こうと思う。塗装もし直さなくては
⑤バンド止めボトルゲージ

LSDトレーニング(*5)として、100km以上走ることもあるので、ボトルゲージをバンド止めしてある
⑥前後ブレーキ

ブレーキレバーはダイアコンペ。以前はダイアコンペのドロップ部に沿わせた脱着式ブレーキレバーを使っていたが、上からレバーを握る時に力不足になりがちだった。また自分はハンドルのセンター部分を握ってロードトレーニングすることが多いので現在のブレーキレバーに交換した。なお、ブレーキ本体はカンパニョーロ・コーラス
[用語解説]
*1ブルホーン及びDHバー ハンドルの形状をいい、タイムトライアル競争などで使用する。
*2ファニーバイク型 フレームが前下がりになった形状
*3クイックレリ-ズレバー ホイールのハブのところにあるレバーで、このレバーを開閉するだけでホイールを簡単にフレームから外したり取り付けたりできる。
*4スケルトン 骨格のこと。つまりフレームの形状及びサイズのこと。
*5 LSDトレーニング 決して、ドラッグを使用してのトレーニングではない。LSDとはロング・スロー・ディスタンス・トレーニングのこと。つまりゆっくりとした速度・負荷で長時間・長距離エクササイズすること。これによって脂肪が効率的に燃焼されると同時に、新陳代謝のよい身体が形成される。春先シーズン初めに行うことが多い。(了)
■ シリーズ一覧(その1) ― 2017/03/12



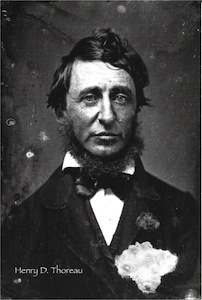


![One's Way[ワンズウェイ]の里山暮らし日記 One's Way[ワンズウェイ]の里山暮らし日記](http://www.ne.jp/asahi/ones/way/images/blog_logo_onesway2.gif)
